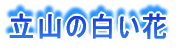 |
| Alpen-plants | |||
 |
 |
 |
 |
| チングルマ(Geum pentapetalum) | |||
| バラ科バラ目ダイコンソウ属(チングルマ属)の落葉小低木。 立山では所々に群生しており、花期は6~8月。白くて可憐な花で花弁は5枚。 高さは10cm程度。枝は地面を這い、群落を作る。葉は羽状複葉。 名前の由来は、花が終わったあとの姿が「稚児車」(風車)に似ていたことから付けられたと云われている。 秋には葉が真っ赤に紅葉し、年間を通じて可憐な姿を楽しむことができる。 |
|||
 |
 |
 |
 |
| タテヤマチングルマ | アオノツガザクラ | ミヤマダイモンジソウ | ハクサンイチゲ |
| 立山稚児車 バラ科ダイコンソウ属。 チングルマの中でも花弁が薄紅色のものをいう。室堂平でも数箇所で見ることが出来る。見ることが出来れば運が良い。 |
青の栂桜 学名:Phyllodoca aleutica ツツジ科ツガザクラ属の常緑小低木。 高さは10~30cm。花期は7~8月。花は淡い黄緑色で壷状の花冠が特徴的。花冠は6~8mmですぼまった先が浅く5裂している。名前は青っぽい花をつけるツガザクラからきている。 |
深山大文字草 学名:Saxifraga fortunei var. incisolobata ユキノシタ科ユキノシタ属 ダイモンジソウの高山型。花茎を直立し、先端に白い花をつけます。花はダイモンジソウのような均整のとれた「大の字」になることは少なく、花弁の長さはバラバラである場合が多い。花期は6~8月。名前は見た目の通り、大文字の形から。 |
白山一華 学名:Anemone narcissiflora キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草。雪渓が解けた跡に群生が見られる。花期は6~8月。白色の花弁に見えるのは萼片で5~7個ある。花弁はない。 |
 |
 |
 |
 |
| ゴゼンタチバナ | エゾシオガマ | ハクサンボウフウ | イワイチョウ |
| 御前橘 学名:Chamaepericlymenum canadense ミズキ科ゴゼンタチバナ属の多年草。 高さ5-15cm。葉は2枚の対生葉と液性の短枝に2個ずつ葉が付き、計6枚の輪生に見える。花期は6~8月。花は4枚の白い総苞に囲まれハナミズキやヤマボウシに似ている。秋にハナミズキに似た赤い果実をつける。和名の「御前橘」は、白山の最高峰「御前峰」に由来している。 |
蝦夷塩竈 学名:Pediculasis yezoensis ゴマノハグサ科 シオガマギク属、半寄生の多年草。 日当たりのよい草地に生える。高さは30~40㎝。葉は長三角形状で羽裂しないが粗い鋸歯がある。下部の葉は対生するが、茎の上半部では互生する。上部の葉腋に黄白色の花がねじれて横向きに咲く。花期は7~9月。 |
白山防風 学名:Peucedanum multivittatum セリ科ヤマゼリ属(カワラボウフウ属) 花期は7~9月。高さは20~70cm。白山で発見され、漢方薬の「防風」に似ていることからこの名がついたとされてる。高さ10cm~50cm。1つの花は径約3mmで、たくさんの花が集まってできた花序の径は約7cm。 |
岩銀杏 学名:Fauria crista-galli ssp. japonica ミツガシワ科イワイチョウ属の多年草。 別名、ミズイチョウ(水銀杏)。 高さ15~30cm。 葉身は腎円形で先がへこみ、縁にそろった鋸歯がある。花は集散状につき、花径1~2cm、花冠裂片は中央に縦のひだ、縁に波状のしわがある。長花柱花と短花柱花がある。花期は5~8月。 |
 |
 |
 |
 |
| イワショウブ | イワツメクサ | タカネツメクサ | マイズルソウ |
| 岩菖蒲 学名:Tofieldia qlutinosa ssp. japonica ユリ科チャボゼキショウ属の多年草。 根茎は短く斜めに出る。黒褐色の繊維がつく。高さ20~30cm。花軸とともに粒状の腺毛を密生し粘着する。 葉は茎の下部に2列つく。 つぼみは紅紫色。花弁は白く、徐々に薄紅色~紅色へ変化する。花期は7~9月。別名ムシトリグサ。 |
岩爪草 ナデシコ科ハコベ属の多年草。 高さ5~20cm。葉は細長く3cmほど。花期は7~9月で、白い花を咲かせる。5弁花であるが、真ん中に深い切れ込みが入っているので花弁が10枚あるように見える。和名は、岩の間から生えるツメクサという意味から付けられた。 |
高嶺爪草 学名:Minuartia arctica ナデシコ科タカネツメクサ属の多年草。 本州中部地方と飯豊山の高山帯に分布する高山植物。花期は7~8月。直径1cmほどの白い5弁花を咲かせる。 |
舞鶴草 学名Maianthemum dilatatum ユリ科マイヅルソウ属に属する多年草。 北海道~九州の山地帯上部から亜高山帯の針葉樹林に多く群生する。 |
 |
 |
 |
 |
| コケモモ | ミネシラユキソウ | ヤマハハコ | ウメバチソウ |
| 苔桃 ツツジ科スノキ属の常緑低木。 樹高は10-40cm程度で、直立した幹はぎっしりと密集している。森林に生息するため、日陰で湿度が高く、また土壌が酸性の場所を好む。耐寒性にすぐれ、-40℃以下でも耐えることができる一方、夏が暑い場所では生育しにくい。初夏に釣鐘型の白い花をつけ、果実は秋に赤く熟す。 |
峰薄雪草 Leontopodium japonicum var. shiroumense キク科ウスユキソウ属に属する。 名前のとおり、薄く雪をかぶったような白い花を咲かせる。ただし、本当の花はごく小さく、花のように見えるのは花序の周囲を飾る苞葉と呼ばれる葉で、その表面に白い綿毛が密生しているため、まるで雪をかぶっているように見える。ヨーロッパアルプスではエーデルワイスと呼ばれる。 |
山母子 Gnaphalium affine キク科ハハコグサ属の越年草である。母子草の一種で春の七草の一つ、「御形(オギョウあるいはゴギョウ)」でもあり、茎葉の若いものを食用にする。 |
梅鉢草 学名:Parnassia palustris ユキノシタ科ウメバチソウ属の多年草。 根出葉は柄があってハート形。高さは10~40cmで、花茎には葉が1枚と花を1個つける。葉は、茎を抱いている。花期は8~10月で2cmほどの白色の花を咲かせる。「梅鉢」とは、紋所(家紋)のひとつで、変形に、中心部がおしべの形ではなく、ただの丸になっている「星梅鉢」がある。菅原道真や前田利家の家紋として有名。 |
 |
 |
 |
 |
| ツマトリソウ | タテヤマリンドウ | モミジカラマツ | ミネズオウ |
| 褄取草 学名: Trientalis europaea サクラソウ科ツマトリソウ属の多年草。 高さ10~20cm。花の径は約1.5 cmで、通常1個つき、花冠は7つに裂ける。花弁の端が淡いピンクで縁取られていることから付いたようである。調べる前は妻取り草だと思ってました。 |
立山竜胆 学名:Gentiana thunbergii var. minor リンドウ科リンドウ属の越年草。 ハルリンドウの高山型変種。 高さは5~10cm。花期は6~8月。漏斗状の淡青紫色の花を、茎の上部に1個つける。花は日があたっている時だけ開き、曇天、雨天時は、筆先の形をした蕾状態になって閉じている。室堂周辺には多く群生しており、シロバナタテヤマリンドウが多いのが特徴。 |
紅葉唐松 キンポウゲ科モミジカラマツ属の宿根草の多年草。 高さは40~60cm。花期は7~8月。根本から高く伸び上がる花茎を出し、その先に散房花序の直径1cmほどの白色の花を多数つける。花弁はなく、白い花は雄しべの集まりである。名前は、花がカラマツの葉の付き方に似ていること、葉がモミジの葉に似ていることから付けられた。 |
峰蘇芳 学名:Loiseleuria procumbens ツツジ科の常緑小低木。 日当たりの良い岩場に生える高山植物。高さは10~15cm。地面を這うように広がる。花期は6~7月。花冠は白色~紅色で5裂している。直径5mmほどの小さく金平糖のような花を咲かせる。和名の蘇芳(スオウ)は、イチイのこと。葉がイチイに似ていること、高い峰に生えることから、由来となっている。 |
 |
 |
 |
 |
| サンカヨウ | オオハナウド | キヌガサソウ | シコタンハコベ |
| 山荷葉 学名:Diphylleia grayi メギ科サンカヨウ属の多年草。 高さは30~70cm。花期は5~7月。茎の先に直径2cmほどの白色の花を数個つける。大小2枚つく葉はフキのような形をしており、花は小さい葉につき、葉の上に乗っているように見える。大きい葉には花がつかない。花のあと、濃い青紫色で白い粉を帯びた実をつける。実は食用になり甘い。 |
大花独活 学名:Heracleum lanatum ssp. asiaticum セリ科ハナウド属の多年草。 高さ1~2m。花弁は5枚のうち2つが長い特徴がある。葉は3裂。花期は7~9月。ハナウドよりも大型で高地に生息する。 |
衣笠草 学名:Kinugasa japonica ユリ科 ツクバネソウ属(キヌガサソウ属)の多年草。 花は直径7cmほど外花被片は7から10枚。花期は6~7月。葉は茎の先に8~10枚輪生し長さ10~25cm。学名に日本名が付いていることからわかるように日本固有種である。 |
S. rusifolia Pall. ナデシコ科、ハコベ属のひとつ 越年草。ハコベラともいって、春の七草の一。イワツメクサもこの仲間である。 |
 |
 |
 |
 |
| オオヒョウタンボク | オニシモツケ | ワタスゲ | ノウゴウイチゴ |
| 大瓢箪木 学名:Lonicera tschonoskii スイカズラ科スイカズラ属の落葉低木。高さは1~2m。花は2cmと小型。白色もしくは薄紅色の花を咲かせる。オオヒョウタンボクの名前は実からきている。赤い実が2つなり、実が触れ合った部分が合着し瓢箪に見えることに由来する。花期は7~8月。実は毒性が強く、ひどい場合には痙攣や昏睡状態となる。別名嫁殺し。今風に言えば夫殺し? |
鬼下野 学名: Filipendula kamtschatica バラ科シモツケソウ属の多年草。 高さは1.5mから2.0mくらい。葉に葉柄があり、茎に互生し、頂小葉は掌状に5裂する。葉柄につく側小葉は目立たないが、葉柄の付け根にある托葉は茎を耳状に抱き目立つ。花期は6月から8月で、白色の小さな5弁花を散房状につける。 |
綿菅 カヤツリグサ科ワタスゲ属の多年草。 別名でスズメノケヤリ(雀の毛槍)という。高さ30~50cm。花期は5月~6月。白い綿毛を付ける果期は6月~8月。花が終わると直径2~3cmの名前の由来ともなっている白い綿毛を付ける。この綿毛は種子の集まりである。 |
能郷苺 学名:Fragaria iinumae バラ科オランダイチゴ属の多年草。 高さ10~15cm。花期は5~7月。太い根茎を持ち、長い走出枝を出す。葉は3小葉からなる複葉で、粗い鋸歯がある。花は径2 cmほどで、他の苺とは違い花弁が多く、7~8枚あるのが特徴。名前は岐阜県の能郷村で発見されたことからくる。 |
 |
 |
 |
 |
| ニリンソウ | ミズバショウ | コバイケソウ | ハクサンシャクナゲ |
| 二輪草 Anemone flaccida キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草。 3月~6月に、白い萼片を持つ花をつける。多くは一本の茎から特徴的に2輪ずつ花茎が伸び、和名の由来となっている。根茎で増えるため、群落を作ることが多い。根茎は「地烏(ジウ)」と呼ばれ、漢方薬として用いられる。 |
水芭蕉 Lysichiton camtschatcense サトイモ科の多年草本。 湿地に自生し、純白の花を咲かせる。開花時期は低地では4月から5月、高地では融雪後の5月-7月にかけて。雄蕊(ゆうずい)と雌蕊(しずい)を持つ両性花である。根茎はかつて腎臓病や便秘などの民間薬として利用されたこともあるが、薬効についての根拠はなく、逆にアルカロイドが含まれているため、服用すると吐き気や脈拍の低下、ひどい時には呼吸困難や心臓麻痺を引き起こす危険があるので利用は禁物である。 |
小梅蕙草 ユリ科シュロソウ属の多年生の植物。 山地から亜高山の草地や湿地のような、比較的湿気の多いところに生える。 名前の由来は、花が梅に似ており、葉が蕙蘭に似ているため。6月から8月に穂の先に白い花をつける。有毒であり、全草にプロトベラトリン等のアルカロイド系の毒成分を持つ。誤食すると嘔吐や痙攣を起こす。 |
白山石楠花 Rhododendron brachycarpum G. Don ツツジ科ツツジ属シャクナゲ亜属の低木。 樹高は、亜高山帯では3mほどにもなるが、ハイマツ帯では環境が厳しいため50cmにも満たない場合がある。花は白から淡い紅色で、内側に薄い緑色の斑点がある。 |
 |
 |
 |
|
| ナナカマド | チョウノスケソウ | ||
|
七竈 |
長之助草 学名:Dryas octopetala バラ科チョウノスケ属の常緑小低木。 質の茎が地面を這う。葉は楕円形で、上面が無毛で下面には白い毛が密生する。夏に数センチの茎の先に花が咲く。花弁は白く、種小名octopetalaは「花弁が8枚」の意味で、普通は8枚あるが16枚の場合もある。雌蕊は多数あり、白い羽毛状で、果実(痩果)になっても残り、これによって風で飛ばされる。日本では須川長之助(ロシア人植物学者マクシモヴィッチの助手)が初めて採集したことからこの名がある。日本のものは一般に変種(var. asiatica)とされる。日本固有種ではない。 |
||
 |
 |
 |
 |
| ミヤマコゴメグサ | ヤグルマソウ | ウラジロタデ | ミヤマセンキュウ |
| 深山小米草 学名:E. insignis Wettst ゴマノハグサ科コゴメグサ属の1年草。 本州近畿以北の亜高山帯~高山帯に分布し、乾燥した草地に生育する。葉は対生で長さ6~12mm。花期は7~9月、花弁は白色で淡紫色を帯びる。 |
矢車草 学名:Rodgersia podophylla ユキノシタ科ヤグルマソウ属の多年草。 低地から亜高山の草地に群生する。 掌状または羽状の複葉で大型の根出葉をもつ。小さい白い花が密集して、大型の円錐花序になる。小葉が5個あり、形が矢車に似ていることから名が付いた。 |
裏白蓼 学名:Aconogonum weyrichii タデ科オンタデ属の多年草。 高山の砂礫地や岩場に生育する。雌雄異株で茎には荒い毛がある。葉の裏に綿毛が密生し白色である。ピンクか赤色の方が雌株。イタドリに似ているがイタドリは高山には生育しない。 |
深山川? 学名:Conioselinum filicinum セリ科ミヤマセンキュウ属の多年草。 亜高山から高山の草地に生育する。高さは30~80cm。葉は2回全裂し、小葉はさらに深裂する。小さな白い花が多数集まって咲く。シラネニンジンと判別が難しい。 |