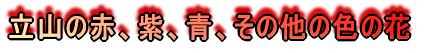 |
 |
 |
 |
 |
| �A�J���m | �x�j�o�i�C�`�S | �������R�E | �C���J�K�~ |
�ԕ� �c�c�W�ȃV���^�}�m�L���̏�Ώ���B �ʖ��̓C���n�[(�≩��)�B ������10�`30cm�B�Ԃ͔��`�W�����F�B�Ԃ̑傫����6�`8mm�Œޏ��`�A����������5�ɗA�y���J�[�����Ă���B�ӂ͂����₩�ȐԐF�����Ă���B�Ԋ���5�`7���B�Ԃ��I�����ӂ��������A�ʎ����ݍ��݁A�ԐF�̋U�ʂƂȂ�B���̋U�ʂ͐H�p�ɂȂ�A�Â݂����肨�������B���O�͐Ԃ�������u�A�J�����i�ԓ��j�v�ƌĂ�A���ꂪ�a���ĕt����ꂽ�Ƃ�����B |
�g��� �w���FRubus spectabilis ssp. Vernus �o���� �L�C�`�S���̗��t��B ����1-1.5m�B�t��3�o���t�B�}��t�Ɏh�͂Ȃ��B�}��ɒ��a2-3�p�̔Z���g�F�̉Ԃ�1�������ɂ���B�ԕق�5���B�Ԋ���7�`8���B���a2-3�p�̐Ԃ��W���ʂ����ԕق͕��J���Ȃ��B |
�ᖒ�g/��؍� �w����Sanguisorba officinalis�B �o���ȁE�������R�E���̐A���B ���n�ɐ����鑽�N�����{�B�Íg�F�̉��ȉԂ�����B�u�����������肽���v�Ƃ͂��Ȃ��v�������߂Ė��Â���ꂽ�Ƃ����B�܂��A�Ԃ������Ŏ��͐Ԃ��ƌ���������A�ᖒ�g�ƂȂ����Ƃ����Ă���B |
�⋾ �w��Schizocodon soldanelloides �C���E���ȃC���J�K�~���̑��N���B ���n����ɌQ������B �t�͊ۂ��A������B�Ԋ��͏t����āB�Ԃ͒W�g�F�ŁA�ԕق�5�ɕ�����A���̐�[�͂���ɍׂ����Ă���B�Ԍs��10�`15cm�ŁA5�`10�ւ̉Ԃ��������ɂ���B���O�́A���ɐ����邱�ƂƁA����̂���t�����Ɍ����Ă��邱�ƂɗR������B |
 |
 |
 |
 |
| �n�N�T���`�h�� | �^�e���}�A�U�~ | �V���E�W���E�o�J�} | �g���J�u�g |
| ���R�璹 �����ȃn�N�T���`�h�����̑��N���̍��R�A���B ������10�`40cm�B�Ԋ���6�`8���Ōs�̐�[�ɑ���ԏ��̐Ԏ��F�̉Ԃ𑽐�����B�Ԋ��͐O�`�ł���A��[��3�Ă���B���O�͔��R�ɑ������ƁA�Ԃ̕t�������璹�̔�Ԏp�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��疼�t����ꂽ�B |
���R�H �L�N�ȃA�U�~���̑��N���B �s�͒����܂��͂��Ώサ�A���F�̓�т��܂�ɂ���A�㔼���Ɏ���̔����т��������A����40�`150�����ɂȂ�B�Ԋ���8�`9���B�s�㕔�ɒ��������o���A�g���F�̓��Ԃ�1������B�Ԃ͉��`��≺�����ɍ炭�B���Ԃ͑����̓���Ԃ���Ȃ�B����Ԃ̐��5��B ��䚕Ђ̊O�Ђ͒���7�`15�����ŁA����ɐ��B ��䚂̊�ɂ�����䚗t������B |
�́X�� �w���F Heloniopsis orientalis �����ȃV���E�W���E�o�J�}���̑��N���B �l���߂��̓c��ڂ̌l�����獂�R�т̍��w�����܂Ő����Ă���B�Ԃ̐F�͐���ꏊ�ɂ���āA�W�g�F�A���F�A���F�ƕω��ɕx��ł���B�Ԋ��͒�R�ł�3�`4���ł��邪�A���R�ł͐�k���n�������Ƃ�6�`7���ɂȂ�B���O�́A�Ԃ��Ԃ��̂��́X�i�����̓`����̓����̂��Ɓj�ɂȂ��炦�A�����t�̏d�Ȃ肪�тɎ��Ă��邱�Ƃ��疼�t����ꂽ�Ƃ����B |
���� �w��Aconitum �L���|�E�Q�ȃg���J�u�g�� ���N���ŁA��Ȃǂ̔�r�I���C�̑����ꏊ���D�ށB�L���ȗL�ŐA���B��ȓŐ����̓A���J���C�h�̈��A�A�R�j�`���ŁA�S���i���ɍ��j�Ɋ܂܂��B�H�ׂ�ƚq�f�≺���E�ċz����Ȃǂ��玀�Ɏ��邱�Ƃ�����B�o��z���E�o�S���z������A�o������ێ�㐔�\���Ŏ��S���鑦����������B��ō܂͂Ȃ��B �g���J�u�g�̖��̗R���́A�Ԃ��×��̈ߑ��ł��钹���E�G�X�q�Ɏ��Ă��邩��Ƃ��A�{�̌{���i�Ƃ����j�Ɏ��Ă��邩��Ƃ������Ă���B |
 |
 |
 |
 |
| �N������ | �N���g�E�q���� | �I���}�����h�E | �~���}�����h�E |
���S�� �w��:Fritillaria camschatcensis �����ȃo�C�����̐A���B�ʏ̃u���b�N�T���i�B ���R�т̑��n�ɐ�����B�Ԋ��͉āB�Ԃ͊����F�ʼnԌa3cm���x�A�ޏ��̌`�������Ԃ��������ɍ炭�̂������B���N���B�n���ɂ��s������A�s��10�`30cm�ɂȂ�B�t�͌ݐ��ł͂��邪�A�ڋ߂��āA2�`3�i�̗���ɂ��B���{�ōł��L���Ȑ����n�͔��R�ŁA��ʂɌQ�����Ă���̂��݂���B |
������� �w���FSaussurea nikoensis var. sessiliflora �L�N�ȃg�E�q�������̑��N���B �V���l�A�U�~�̕ώ�B����30-60�p�B�V���l�A�U�~��蓪�Ԃ������傫���ĂقƂ�ljԕ��͂Ȃ��A2-3�̓��Ԃ��s�̐�ɂ���B��䚂͈Î��F�B�t�͒����S�`�łЂ�ƂȂ��Čs�ɗ����B |
��R���_ Gentiana makinoi �R�n�̈����R�сA���n��n�ɐ����郊���h�E�ȃ����h�E���̑��N���A���B �H�̎������\����Ԃ̈�B |
�[�R���_ �����h�E�ȃ����h�E���̑��N���̍��R�A���B �k�C���`�����n���Ȗk�̍��R�̂�⎼�������n�ɐ�����B������5�`10cm�B�Ԋ���7�`9���Ōs�̏㕔�ɐ��F�̉Ԃ�4�قǕt����B�Ԋ���5�ɗĂ�����Ђ̊Ԃɏ��������Ђ�����B |
 |
 |
 |
 |
| �C���M�L���E | �^�J�l�E�X���L�\�E | �V���c�P�\�E | �~���}�N���K�^ |
��j�[ �w��:Campanula lasiocarpa �L�L���E�ȃz�^���u�N�����̑��N���B ���I�n��n�ɌQ������̂�������B����10cm�قǁB�t�͑����ōג����A1.5�`3cm�B�Ԋ���7�`8���B����̊��ɂ͑傫�Ȑ��F�̉Ԃ��������ɍ炩����B�{��Ƃ悭������Ƀ`�V�}�M�L���E������B�`�V�}�M�L���E�̉Ԃɂ͑@�т������Ă��邪�A�{��ɂ͐����Ă��Ȃ��̂Ō����������B |
���䔖�ᑐ Anaphalis alpicola Makino �L�N�ȃ��}�n�n�R���̑��N���B ���������n�Ȃǂɐ��炷��B����10�`12cm�B�t�͌ݐ��Œ���4�`6cm�A�D���F�̖Ȗт������Ă���B�Ԋ���8���B���F�ʼn������W�g�F�̉Ԃ����� |
���쑐 Filipendula multijuga |
�[�R�L�` �w���FVeronica schmidtiana ssp. senanensis �S�}�m�n�O�T�ȃ����g���m�I�� �i�N���K�^�\�E���j�̑��N���B �s�͕��}�����������A�e�т�����B�t�͌s�̉����ɏW�܂��Ă���A�X�v�[���`�Ő�͂Ƃ����Ă��āA���ɂ͕s���낢�̋���������B���ɂ͕s���낢�̋���������A���ʂƂ����тɋ߂��B�Ԋ��͐[���S�A2�{�̗Y���ׂƎ����ׂ��Ԋ���蒷���˂��o�Ă���B |
 |
 |
 |
 |
| �V���l�A�I�C | �~�\�K���\�E | �e�K�^�`�h�� | ���c�o�V�I�K�} |
| ������ Glaucidium palmatum �L���|�E�Q�ȃV���l�A�I�C���̑��N���B �[�R�̐A���B���{�ŗL���1��1��ł���B ������20�`30cm�B�Ԋ���5�`7�����B�ԕق͂Ȃ��A7cm�قǂ̒W�����F�̑傫���ӕЂ�4������A��ϔ������p�����Ă���B���O�́A���������R�ɑ����A�Ԃ��^�`�A�I�C�Ɏ��邱�Ƃ���V���l�A�I�C�Ɩ��Â���ꂽ�B �ʖ��R���u�A�t���u�B |
���X�쑐 �w���FNepeta subsessilis �V�\��. �Ԋ���7�`9����{�B����50 cm�`1 m���x�B4�p�ő����s����������B�t�͐悪�s����������`�ŁA���ɋ���������A�ΐ�����B�ԕ�ɒW���F�̉Ԃ��������B�Ԋ��͏㉺�Q�O�ɕ�����A��O�͂��ԂƏ�ɂӂ���݁A�����ۂ����O��3�A�������ЂɎ��F�̔��_������B���O�͖ؑ]��̎x���̖��X��t�߂ɑ������Ƃ���B ���邢�͗t���ɂ���B����o�����ȏL�C�ɂ��. |
��`�璹 �w���FGymnadenia conopsea �����ȃe�K�^�`�h�����̑��N���B �ʖ��`�h���\�E�Ƃ������B ������30cm����60cm�B�Ԋ���7�`8���B1cm���x�̏����ȉԂ����ɖ��W���č炭�B�Ԃ̐F�͒W���g���F�B���O�͉Ԃ��璹�̔�Ԏp�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���t�����Ă���B�ގ���Ƃ��āA�m�r�l�`�h���ƃn�N�T���`�h��������B�m�r�l�`�h���͗t�̉����g�ł��Ă��邱�ƁA�n�N�T���`�h���͉Ԃ̐�[������Ă��邱�ƁA�S�ʓI�Ƀe�K�^�`�h���̕����Ԃ̐F���W���X�������邱�Ƃ��环�ʂł���B |
�l�t���� �w���FPedicularis chamissonis var. japonica �S�}�m�n�O�T�Ȃɑ����鑽�N���̍��R�A���ŁB �V�I�K�}�M�N�̒��Ԃł͍ł��悭�������ł���B�����̃~���}�V�I�K�}�Ȃǂ����Ȃǂɐ�����̂ɑ��A���c�o�V�I�K�}�͎��n�тɐ�����B������20�`50cm�B���O�̗R���̂Ƃ���A�V�_�̂悤�ȗt���s�̐߂��Ƃ�4��������B�Ԋ���6�`8���ŁA�����F�̑����ĒZ���ԕق����i�ɏd�Ȃ������B |
 |
 |
 |
 |
| �n�N�T���t�E�� | �~���}�I�_�}�L | �^�J�l�}�c���V�\�E | ���L�����\�E |
| ���R���I Geranium yesoemse var. nipponicum �t�E���\�E�ȃt�E���\�E���̑��N���B ���R�̐�k���ӂ̑��n�ɐ�����B������50cm���x�B�Ԋ���7�`8���B�ԐF�͍g���F�B�ԕق�5���B |
�[�R���� A. flabellata var. pumila �L���|�E�Q�ȃI�_�}�L���̑��N���B�s�͍���10�`25cm�قǁA�Ԋ���6�`8���Ő�[�ɐ��ւ̉Ԃ����ނ������ɂ���B�Ԃ͐��F�A�ӕЂ͍L���`�ŎP��ɊJ���A�ԕق͉~���`�ɂ܂Ƃ܂��ĕt���A��[�͂�┒���ۂ��A�������ӂ̊Ԃ��ċ����̂т�B �a���̗R���́A���Ƃ����a�����������ۂ���������Ԃ̌`�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���t����ꂽ�B |
���䏼���� �}�c���V�\�E�ȃ}�c���V�\�E�� �}�c���V�\�E�͒�n���爟���R�ɐ��炷�邪�A�^�J�l�}�c���V�\�E�͍��R�n�т̑��n�ɐ��炷��B�����30�`40�����Ń}�c���V�\�E���Ⴍ�A���Ԃ��傫���̂������B �Ԃ��I��������Ƃ������ނɎ��Ă��邱�Ƃ��疽���B |
�ኄ�� |
 |
|||
| �m�R���M�N | |||
| �썮�e �w���FAster ageratoides �L�N�ȃV�I�����̑��N���B �n���s���L�тĔɖ���A��n�ł͌s�͒���40�`100�����ƂȂ邪���n�ł�20�`60�������x�B �㕔�Ŏ}�����ꂷ�� �t�́A�ݐ��A���ȉ~�`�A��[�͂����A�t�ɂ͐�����������A���ʂɂ͑e���т�����A���炴�炷�� �Ԃ́A8�`11������܂ō炫�A�s���ɐ��̎��ӂɒW���F�`���F�̐��ԁA�����ɉ��F�̓��i�ǁj��Ԃ����� |
|||
| ���f�� | |||
| �`�V�}�M�L���E ���}�z�^���u�N�� �n�N�T���R�U�N�� �~���}�n���V���E�Y�� |
�ʐ^���Ȃ����߁A����܂�����Čf�ڂ��܂��B | ||